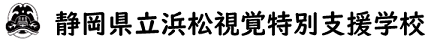令和8年1月
寄宿舎での自立活動研修会
1月23日(金)、本校寄宿舎で研修会を行いました。テーマは「視覚に障害のある方への配膳指導の仕方」でした。本校専攻科の教員(全盲)に講師をお願いし、味噌汁を鍋から汁椀によそう時の支援のポイントについて、研修をしました。アイマスクをして実際に鍋に入ったスポンジやビー玉をおたまですくい、適量を汁椀によそうというものでしたが、姿勢の保持、よそう時には立った方がやりやすい、おたまを水平に保つなど、参考になることがたくさんありました。その後も食事や生活に関して、日頃の支援で悩んでいることについて一問一答式で教えていただき、とても有意義な時間になりました。

令和7年度8月
第5回浜See塾~開催
夏休みの研修の機会を活用して、教職員を対象としたミニ学習会(浜See塾)を開催しました。今回は昨年に引き続き、視覚障害者の方と気軽に話せる座談会という形式でのを開催でした。本校教職員の当事者をゲストに招き、進路や学生時代の思い出、一人暮らしの苦労など、さまざまな内容を織り交ぜたお話を伺いました。
普段なかなか聞けないプライベートな話題について充実したトークができ、当事者の思いについて理解を深めるとともに、幼児児童生徒の指導につなげる良い機会となりました。

令和7年度6月
教職員対象~第3回浜See塾~開催
令和6年度から新しい取り組みとして、教職員の視覚障害教育の専門性向上を目的としたミニ学習会「浜See塾」を行っています。
4月は第1回「ぼやけの程度と視力測定のやり方」、5月は第2回「コントラスト感度」をテーマに実施しました。 そして今月開催された第3回のテーマは、「MN‐READのやり方を知ろう」でした。MN‐READとは、文章を読んで最大読(書)速度や臨界文字サイズを計測するものです。それをやることにより、その人の読書に必要な文字サイズ(同じ視力でも人によって異なることがある)がわかり、客観的な評価をもとにプリントや教科書等の文字サイズを考えることができます。受講を希望する先生が多く、今回は2回に分けての実施となりました。
今後も様々なテーマでミニ学習会を開き、教職員の専門性の向上につなげます。



令和7年度4月
見えにくさについて学びました
4月に行った新任者研修を紹介します。
4月18日に視能訓練士の田中恵津子先生を講師に迎え、「ロービジョンに対する支援」というテーマでお話をいただきました。
研修を通して、幼児児童生徒の見えにくさを理解するためには、「ぼやけの程度はどのくらいか」や「見える範囲はどの程度か」、「視線の先が消える」「コントラストの感度はどの程度か」「まぶしさを感じるか」などを、総合的に評価してとらえていく必要があることを学びました。また、田中先生から、見えにくさに伴う困難を解決するための手立てを、見えにくさの観点別にたくさん例示していただきました。これから幼児児童生徒とかかわる中で、個々の見え方に応じ、適切な支援を講じられるよう、今後も研修に努めていきます。
4月の新任者研修の一場面




足の感覚を研ぎ澄ませて歩きます
本校の食堂の床面には、1本のロープが張りつけられています。このロープは、児童生徒や教職員の食堂内での移動経路(動線)を表しています。多くの人が集まって、食事の席についたり、食器を洗って返却口に食器をかたづけたりするため、食堂内では、一方通行が基本のルールとなっています。止まるとき、動くとき、洗い場が空いたとき、お互いに声を掛け合って安全を確かめ合う姿は、見えにくさを持つ児童生徒、教職員が集う本校ならでは光景かと思います。本校には、そのロープの盛り上がりを手掛かりにして歩いている児童生徒・教職員がいます。足でそのロープの盛り上がりを感じ、ロープに沿って進んだり曲がったりします。安全に歩くために足の感覚を研ぎ澄ませています。


教職員対象のミニ学習会開催
9月20日(金)、NPO法人 六星 障害者授産所ウイズ蜆塚施設長 古橋友則氏を講師にお迎えし、ロービジョンの方の歩行指導をテーマに研修を行いました。
研修では、ロービジョンの方が歩行の際に抱く困り感や、それを軽減・克服するために必要なスキルについて学習しました。
さらに、プラスチックのカップを使ってロービジョンの方の見え方を擬似体験しながら校内を歩行しました。体験を通して、校内の案内板や非常用ヘルメットの位置がわかりにくいことや、見えにくい状態を言葉で説明することの難しさに気付くことができました。