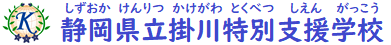公開日 2024年06月13日
6月7日(金)歯と口の健康週間(4~10日)カルシウム強化献立
「ひじきごはん、和風ハンバーグ、小松菜のなめたけ和え、切干大根のみそ汁、牛乳」
ひじきの栄養といえば「鉄分」や「食物繊維」です。鉄分は酸素を全身に運ぶために必要な栄養です。不足すると頭痛やぐったりと疲れてしまう症状がでます。不足しないように食べてください。人参、こんにゃく、しいたけ、鶏肉と炒めて調味し、ご飯と混ぜてまぜごはんとして提供しました。


6月10日(月)入梅献立
「麦ごはん、炒り豆腐、きゅうりの南蛮漬け、じゃがいものみそ汁、青梅ゼリー、牛乳」
10日は「入梅」。梅雨の季節です。今年の梅雨入りはまだですが、梅の実が黄色く熟す頃に長雨になることから、この字があてられたと言われています。熟した梅からは、梅干しや梅酒、梅シロップなどが作られます。給食のデザートは梅を使った、さっぱりとした青梅ゼリーでした。


6月11日(火)
「ごはん、鶏肉の薬味ソースがけ、牛肉とごぼうの炒め煮、油揚げのみそ汁、牛乳」
毎年6月は「食育月間」となっています。食育基本法が成立した月が平成17年6月であることや、学校生活や社会生活等の 節目に当たる年度明けの時期で、進学や就職、転勤等の影響が少ない月が適当 だということで、6月が食育月間となりました。さまざまな経験や学習を通して、食に関する正しい知識と、食を適切に選ぶ力を身に付け、健康で心豊かな食生活を送ることができるようになってほしいものです。


6月12日(水)
「ごはん、じゃじゃ揚げ、ミニトマト、五目汁、牛乳」
掛川市、菊川市、御前崎市では、トマトの生産がとても盛んです。トマトの原産地は南アメリカのアンデスの高地です。1530年頃にスペイン人の航海家によって、ジャガイモと共にヨーロッパに伝わりました。18世紀に日本に入ってきたトマトは、最初鑑賞用として栽培され、明治の初期に食用として栽培され始めました。当日は、菊川市産の新鮮なミニトマトを味わいました。
6月13日(木)
「ロールパン、グラタン、甘夏サラダ、マセドアンスープ、みかんジャム、牛乳」
6月1日は国連食糧農業機関(FAO)が提唱する「世界牛乳の日」です。2007年に日本でもこれに合わせて6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」としています。日本で最初に牛乳が飲まれたのは飛鳥・奈良時代。食生活に根付いてきたのは高度経済成長期以降です。牛乳は鮮度が大切なので、実は地域密着型の食品でもあります。また、季節や牛が食べるエサによって味わいも変化します。